よくあるご質問
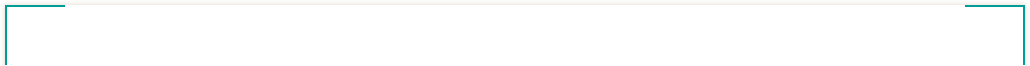
衛生関連製品
-
「抗菌」は「殺菌」とか「消毒」とは違いますか -

「抗菌」とよく混同しやすい言葉に、「滅菌」「殺菌」「消毒」などがあります。「滅菌」「殺菌」「消毒」という言葉は、いずれも微生物を完全に死滅させるか、除去することを意味するのに対し、「抗菌」は細菌の増殖を抑制することを意味していて全く意味が異なります。医療の現場では、病原性のある微生物を完全に死滅もしくは除去する必要性があり、これらの言葉が使用されていますが、そのような医療用語と「抗菌」とは区別しています。したがって、協議会による抗菌加工表面には、悪玉もしくは善玉いずれの細菌であっても増殖を抑制する緩やかな効果があるだけで、完全に死滅させたり除去したりするような強い殺菌作用ではありません。時々マスコミ等で「抗菌加工を施すと我々に有用な善玉菌まで全滅させてしまうから有害無益だ」といったような記事を目にしますが、このような内容は誤っていますのでご注意ください。
-
「抗菌」や「抗菌加工」とはどのような定義で、どのような意義がありますか -

抗菌JIS Z2801によれば、抗菌とは「製品の表面における細菌の増殖を抑制する状態」と定義され、製品表面の細菌数を測定しそれが抗菌状態であるかどうかの判定方法が記載されています。通常の環境下では、細菌は指数関数的に増殖するのが通例ですが、抗菌加工とは、抗菌加工された表面の菌数が始め状態のまま保たれ殆ど増減のないことを意味しています。
-
協議会に登録された抗菌加工製品を日常生活で使用すると、どのような利点がありますか -

協議会の取り決めた基準によれば、抗菌加工された製品表面での細菌の増殖の状況は、製品表面を清浄にさえしていれば、抗菌加工されていない表面と比較し、安全面は変わらないで、しかもその製品が使用される期間中常に細菌の増殖割合のみが百分の一以下に保たれていることです。
一般的に、私どもは日頃細菌と慣れ親しみ、細菌とともに生活しているとい言っても過言ではないでしょう。細菌の中には、最近マスコミ等で騒がれている食中毒菌や病原菌もあるし、また常在菌といわれる、私ども自身又は周囲にいつも共生し悪影響を及ぼさない善い細菌もあります。また、悪い細菌であっても、それ程数が多くなければ害は及ぼしません。
しかしながら、いずれの細菌も生育条件が整えば指数関数的に増殖し、善い細菌はそれでも問題はありませんが、悪い細菌の例では、悪臭、ぬめり、もしくは食中毒、病気等生活環境の悪化や健康被害に繋がることが問題となります。
ところが、協議会に登録された抗菌加工製品の表面では、前述したような細菌が原因で起こる様々な私共に具合の悪い現象が起こり難くなり、しかも安全上も安心なことが特徴であり、これこそが抗菌加工製品の利点と言えます。以上のような理由で、細菌が増殖し易い環境下で使用する製品には、とくに抗菌加工された製品をお奨めします。 一方、抗菌加工は、「無菌」「殺菌」「消毒」のように細菌を完全に殺してゼロにする効果はありません。したがって、抗菌加工製品を使用しても無菌状態になるわけではありませんので、食中毒を完全に防止するような効能も謳えないかわりに、多用したとしてもヒトの免疫力が低下するというような心配もありません
-
衛生関連製品の安全性はどのように確認されているのですか -

剤の安全性試験としては、急性経口毒性試験、皮膚一次刺激性試験、変異原性試験および皮膚感作性試験の4項目があります。それぞれ公的機関またはそれに準ずる機関で所定の方法により試験を行い、基準を満たしていることが必要です。また加工製品にはこの安全性基準を満たした剤を使用しなければなりません。
-
抗菌剤を使用することにより化学物質過敏症になる心配はありませんか -

化学物質過敏症については種々の要素が関与しており、学問的にはまだほとんど明らかになっていません。現在問題にされている化学物質はホルマリンのような揮発性の大きいものが多いようです。
-
抗菌加工製品は抗菌加工されている表面が汚染されても効果がありますか -

抗菌加工された製品では病原菌は増殖しないので汚れた状態のままで使用しても良いかとの問い合わせが時々ありますが、これは誤った解釈です。前述しましたように、製品表面が抗菌加工されていますので、その表面が汚染された場合肝心の抗菌加工表面が汚染物により覆われ所定の抗菌効果を発揮しないことになります。従って、十分な効果を発揮させるには抗菌加工表面を常に清潔に保つ必要があることを理解しなければなりません。
-
「抗菌、防カビ、抗ウイルス、抗バイオフィルム」などの衛生関連加工製品は取扱上で特に注意することはありますか? -

「抗菌、防カビ、抗ウイルス、抗バイオフィルム」などの衛生関連加工製品は、その取り扱いを特別注意する必要はありません。日常使われている製品、例えばまな板、スポンジたわしや便座のようなものの内、衛生加工処理されている商品のことを意味します。これらの商品は、その商品の通常の扱い方で十分です。しかしながら、「衛生関連加工製品」だからといって付着した汚物を洗わずにそのまま継続して使用するようなことは避けなければなりません。なお、商品により取扱上注意が必要な場合は、商品またはパンフレット等に記載されていますのでよくご覧の上使用してください。
SIAAマーク
-
「SIAA」と「SIAAマーク」は何の略で、どう違いますか -

SIAAには、協議会の英語名「Society of International sustaining growth for Antimicrobial Articles」と、協議会自主基準に適合しているとの証である協議会マークの英語名「Symbol of International Certificate for Antimicrobial Articles」の2種類があり、何れも頭文字をとるとSIAAとなり、「エスアイエーエー」と呼称します。
SIAAマーク制度は1999年から実施していますが、抗菌JIS Z 2801制定に伴い、抗菌加工製品については従来のマークに代わり新しい「抗菌JIS Z 2801適合SIAAマーク」が表示できるようになりました。また、2007年には抗菌試験法国際標準ISO22196が正式に発行され、SIAAのマークデザインも新しくなり、ISO22196が表示可能になりました。
抗菌剤についてもFor KOHKINと表示のあるSIAAマークが使用できます。「防カビ」「抗ウイルス」「抗バイオフィルム」についても各マークが利用可能です。
-
SIAAマークにはどのような意味がありますか -

SIAAマークは、その製品が協議会自主基準に沿って自主管理されていることを意味し、「性能」、「安全性」、「適切な表示」の3つの基準を満たした製品の証です。
いずれもそのマークを表示することよって、その製品が協議会自主基準に沿って自主管理されていることを意味し、且つその製品に使用されている抗菌剤の種類、加工方法および加工部位を表示することにより、消費者がより良い品質と安全性を確保した抗菌製品を適切に選択できるようにしたものであり、最終的には関連業界の健全な発展および国民生活の向上に寄与する事を目的としたものです。
-
SIAAマークはどのようなところに,どのような方法で使われていますか -

その製品が協議会自主基準に適合し、かつ表示の具体案を提示の上マーク表示したいとの会員からの申請をSIAAが受理すると、協議会が権利を所有するSIAAマークが使用できます。そのマークの詳細はSIAA規定により決められ、定められた規定の範囲で会員は製品本体、包装材料及び販促資料等に印刷等で表示することができます。なお、協議会ではSIIAの印刷マークの販売は行っておりません。
-
SIAAマークが表示できるのは、どのような範囲の製品が対象ですか -

プラスチック等の非多孔質製品が主な登録の対象です。ただし、薬機法対象製品、農薬取締法や毒物劇物取締法に係わる剤もしくはその剤を使用した加工製品は対象外です。詳しくは、規定「登録加工製品の対象範囲に関する規定」を参照ください。
-
SIAAマーク表示製品にはどのようなものがあるかは、どこで調れられますか -

このホームページの「登録加工製品検索」をクリックしてください。
-
SIAAマークはいつ頃から使用されるようになりましたか -

SIAAマークは、抗菌SIAAマークは1999年1月から運用が始まり、同じ月に第1号の製品が登録されました。2007年には抗菌試験法のISO 22196が発行され、ISO番号付きの抗菌SIAAのマークもできました。登録製品のカテゴリーが増え、2014年から防カビマーク、2019年から抗ウイルスマーク、2024年から抗バイオフィルムマークの運用を始めています。
-
SIAAマーク表示のある商品を購入したいのですが、どのようにすれば購入できるか教えてください -

このホームページの「登録加工製品検索」画面から本会に登録されている商品が検索できます。この中でお探しの製品のジャンルをクリックし,ご希望の製品がございましたら事務局までご連絡ください。会員メーカー様の連絡先をご案内いたします。
-
ペット用の雑貨品にもSIAAマークが表示できますか -

可能です。ただし「ペット用食器」のような登録対象外の製品が一部あり、これにはSIAAマークを表示できません。
協議会の活動
-
「協議会」はどのような経緯で発足しましたか -

抗菌加工製品の普及に伴い、マスコミ等でその性能、安全性、使い方などについて問題提起されることが多くなりました。1993年に発足した無機抗菌剤メーカーの集まりであった銀等無機抗菌剤研究会を基盤として、これを更により広い範囲かつ消費者に近づいた活動を目指し、抗菌加工製品メーカーはもとより抗菌剤メーカー他関連業種の幅広い賛同を得て組織を発展的に拡大した結果、1998年6月協議会として新に発足するに至りました。
-
協議会組織にある「SIAA向上専門委員会」は、今までの業界団体にない消費者や流通業界の意見を反映させる委員会と伺っていますが、委員会の活動目的、活動内容及び構成メンバー等を教えてください -

「SIAA向上専門委員会」は、通産省(当時)が発行した「抗菌加工製品ガイドライン」に基づき、協議会組織内に設けられた委員会で、学識経験者・消費者団体代表・行政関係者・会員企業から構成され、ここで討議された内容や意見を協議会活動に反映させることがその目的です。該委員会の主な議題は、中期計画、事業報告と計画、新しい制度運用、アンケート結果、ホームページでの情報公開のあり方等です。開かれたかつユニークな業界団体として今後もより多くの皆様の声を取り入れて運用していきます。
-
委員会の種類とその活動概要について教えてください -

協議会は委員会が活動の中心を担っています。委員会は、国内外の普及・広報を担う委員会と、新たな試験方法を開発しそれを基に運用する技術系の委員会に大別できます。その他には、中期計画を策定しその進捗を管理する「中期計画戦略委員会」やISO化を担う「国際標準化委員会」があります。これらの委員会は、いずれも開かれた委員会で会員の希望があれば委員長判断で参加できます。それぞれの委員長は、委員会を運営する上で協議会全体の流れを理解している必要があるため協議会理事会で選任されます。
-
協議会が決めた自主基準を会員自ら自己認証できるよう各会員が自ら管理責任者を選任しますが、その人達に対して協議会が実施する教育制度の概要を教えてください。 -

会員は、自社の提供する製品について「品質と安全に関する自主基準」に適合していることを保証し、且つ客先からクレームや問い合わせに対し責任ある措置が取れるよう「管理責任者」を置くことが義務付けられています。選任された管理責任者がその職務を遂行できるよう、それに必要な知識や情報等を入手できるよう、「管理責任者講習会」を開催しています。また、レベルアップのため少なくとも2年に1度「フォローアップ研修」を受講していただきます。
-
「協議会」はどのような団体で、活動内容とこれから目指す活動を教えてください -

協議会は、細菌・ウイルス・カビなどに関する衛生について、消費者に安心・安全・快適を提供することにより、関連業界の健全な発展及び消費者の生活向上に寄与するために活動しています。剤メーカー、加工製品メーカー,試験機関が会員となっており、抗菌剤等の衛生に係わる剤やそれらを用いた加工製品の性能や安全性に関する規格・基準及びその表示法を定め、消費者から信頼される加工製品を提供し、併せて消費者が正しく商品選択できるよう情報公開しています。
-
行政や関連団体とはどのような関係になっていますか -

協議会の会則で「本会は、会員がより良い品質と安全性を確保した抗菌加工製品を消費者に安定して供給できるようーーー」とあるように、抗菌加工製品及びその原料中間製品を扱う巾広い業種会員からの開かれた任意業界団体です。
製品を使用する消費者の皆さんから信頼される製品を安定して提供することが業界の発展とひいては国民生活の向上に寄与することを活動の目的に掲げていますので、経済省、厚生労働省、農水省、公正取引委員会および東京都を中心とする地方自治体、また消費者団体や、大学、学会、研究機関からの学識経験者等巾広い機関及び関係者からご指導頂くと共に緊密な連携の下に活動を進めています。
さらに、特定の製品群を扱っている工業会と協議会は基準策定活動で重複が生じることがあります。即ち、協議会はそれぞれの工業会が扱う製品群を抗菌という機能で見ることとなりますので、協議会が策定する基準は最大公約的性格にならざるを得ません。従って、工業会基準は協議会基準を準用するか、もしくは扱う製品によっては本会基準に上乗せが必要と思われますが、いずれを採用するかは工業会の独自の判断になると考えられます。協議会は、工業会の自主ルール策定には申し出があればそれに協力する用意があります。
-
抗菌剤にはいろいろな種類があると聞いていますが、これら決まった試験法と基準値のみで安全性を本当に確認できるものでしょうか。また使用抗菌剤名は開示頂けますか -

協議会では、前述の安全基準を満たした抗菌剤を使用すること、及び抗菌加工製品に使用される抗菌剤濃度は前記試験で安全性が確認された抗菌剤濃度の半分以下で使用することを定めています。消費者の皆さんが直接触れるのは抗菌加工製品であり、抗菌剤そのものは一般消費者の手元にはいきません。協議会では、このように抗菌剤の安全性確認とその使用濃度の両者で抗菌加工製品の安全性を確認しています。また、協議会発足以来、協議会会員製品の事故例に関する情報は入手していません。
また、使用抗菌剤は、大まかにグループ分けした大分類(4分類)により抗菌加工製品に表示されます。さらに申し出があれば、さらに化学的性質が分る中分類まで開示できます。
-
抗菌加工製品に関する情報が「協議会ホームページ」に掲載されていることを知りました。どのような情報が掲載されていますか教えてください -

SIAAホームページは以下のような内容で構成されています。
・エンドユーザーである消費者の皆様に、抗菌加工製品に関する基礎知識と、商品情報、自主登録のディスクロージャー
・会員企業の皆様には、専用ページにて登録状況と、会員同士の対話の場
などを提供しています。
-
経済産業省の「抗菌加工製品ガイドライン」と「協議会自主基準」とはどのように関連しますか -

「ガイドライン」は抗菌加工製品に求められる抗菌性能及びその持続性、安全性、表示方法等全てに対する基本的指針が示されていますが、具体的な規格・基準までの記載はありません。このうち、抗菌性能のみは、試験方法とその判定基準が抗菌JIS Z2801(2000年12月制定)で規定されましたが、その他の品質性能については業界の自主基準に委ねられています。「協議会自主基準」は、このような「ガイドライン」の考え方に基づき、抗菌加工製品に求められる全ての品質・性能を業界自主基準として規格・基準化したもので、この自主基準に適合したSIAA会員製品にはSIAAが許諾する「SIAAマーク」を表示できます。
入会ご検討
-
SIAAマークは誰でも使用できますか -

SIAAマークを使用できるのは、剤又は加工製品を本会に自主登録した正会員です。正会員は「SIAA マーク管理運用規定」に従って、登録製品にSIAAマークを表示できます。
-
マークを表示するとどんなメリットがありますか -

消費者に信頼される抗菌関連製品であることを意味します。このマークが表示された抗菌関連製品は協議会が制定したガイドラインに従って自主管理されている製品ですので、消費者は安心してその製品を商品選択することができます。
-
SIAAマークを表示するにはどのような手続きが必要ですか -

当該製品が協議会規定「品質と安全性に関する自主基準」に適合していることを証明するため、所定の自主登録データシート、および製品や販促資料に対するSIAAマーク表示個所と表示例―ゲラ刷りーを添付して本会に申請し、それが受理されればSIAAマークを表示できます。
-
SIAAマークをつけた商品を出すまでの簡単な流れを教えてください。 -

SIAAマークはSIAAの商標登録マークですので、このマークを表示するにはSIAAに製品を登録し入会する必要があります。以下、マーク表示商品を店頭に出すまでの流れを説明します。 1.入会申請 入会申込書、誓約書、自主登録データシート、試験報告書の写し等を事務局に提出(自主登録データシートは、登録製品によってフォーマットが異なります。) 2.提出書類の審査 事務局で基準に適合していることを確認の後、理事会の審議に。 3.入会許諾 入会承認を得た後、この旨を申請者に連絡。 4.申請者は、所定の入会金・年会費のお支払い。 5.以上1~4の手続きを完了後、申請商品にSIAAマーク表示販売が可能。
詳細は「入会のご案内」(https://www.kohkin.net/guide.html)及びK09「入会規定」を参照ください。
-
SIAAマーク申請に要する日数と費用について教えてください -

1)日数: 書類提出後、①受理…会の規定に適合しているかの事務局確認、②審議…理事による審議、③決裁…入会の可否、までに約1か月を見込んでおります。
2)費用: 必要費用は、協議会への入会金、毎年の年会費のみとなっております。追加や変更申請に伴う費用や維持費はございません。ただし、自主登録に伴いデータシート記載に必要な試験データを取得するための費用は会員の負担となります。
-
どのような企業が入会できますか、費用はどの程度かかりますか -

協議会の趣旨に賛同し、登録対象の剤又は加工製品製造あるいは販売する法人であれば、製品登録することにより正会員として入会できます。正会員の費用は、初年度は入会金10万円(国内外)と年会費10万円(国内企業)、20万円(海外企業)です(2025年現在)。
賛助会員(試験機関)や準会員(製品登録なし)としての入会もできますので、この場合はお問い合わせください。
-
マーク使用申請が受理され、製品登録になった場合、いつまで有効ですか -

マーク表示は、本会会員がその製品を自主管理していることを意味します。従って、製品登録中止もしくはSIAAマーク管理運用規定に違反しない限り期限の制約はありません。
-
輸入製品にSIAAマークを表示するにはどうすれば良いですか -

輸入製品を国内で販売する日本法人格の輸入業者や販売業者が協議会に入会し、該製品を自主登録すればSIAAマークを表示できます。
-
SIAAマークは自己認証マークとのことですが、従来業界でよく使われている認定マークとどのように違うか教えてください -

SIAAマークは、協議会会員が市場に提供する抗菌剤等の衛生関連の剤やそれらを用いた加工製品が本会自主基準に適合しているとの証で、会員は市場に提供する当該製品にSIAAマークを表示することができます。
自主登録された当該製品が、その後も自主基準に適合しているかどうか、本会は会員に対し管理責任者講習会や定期的性能チェックを実施し、消費者から信頼される製品を市場に提供できるよう努めていますが、製品品質はそれら製品を提供する会員が管理します。
自己認証とは、当該製品を提供している会員自ら本会自主基準適合を宣言したマークの意味です。
-
外国企業が自国で製造した抗菌剤や抗菌製品を、日本でSIAAマークを表示し販売するため入会することができますか -

海外の企業でも、抗菌剤や抗菌加工製品の抗菌性能値および安全性のデータがSIAAの基準に適合していれば、入会しSIAAマークを表示し販売することができます。
-
会員であれば、デパートや量販店で販売製品にSIAAマークを表示することができますか -

協議会の正会員である販売会社の名称が明示されていれば、SIAAマークの表示(自主登録)ができます。
申請について
-
管理責任者になるためには特定の受験資格が必要ですか?またどうすればなれるか教えてください -

管理責任者には、特定の資格、あるいは役職者である必要はありません。管理責任者は自社内で選任され、入会後1年以内に、協議会が定める講習会を受講し、協議会の認定を受けなければなりません。
-
アクセスできないページがあります。どうすれば見ることができますか。 -

会員向けお知らせや運用マニュアル等は、会員のみに公開しています。
-
管理責任者は一度認定を受ければ、いつまでも有効ですか -

フォローアップ研修会には2年に一度以上参加することが義務付けられています。 SIAAの制度、品質管理や法令遵守等、管理責任者として必要な知識や最新情報の収集に努める必要があります。
-
管理責任者は会員企業組織の内部に限られるでしょうか? -

管理責任者は、会員企業にあって協議会ルールに沿った当該製品を提供する責任を担う事となりますので、それを果すことが出来る方である必要があります。このような本職務の性格からみて、組織内部から選任し、入会時に届出しなければなりません。
-
会員各自が選任している管理責任者にはどのような責任がありますか -

管理責任者は自社で生産あるいは販売しているSIAA登録製品に関する品質、安全性、表示、法令遵守、利用方法等について責任を有しています。
-
管理責任者になるには、どの程度の時間と費用が必要ですか? -

入会後1年以内に、本会が定める管理責任者講習を受講し、認定を受けなければなりません。この講習会は有料で、1日の日程で受講します。なお、認定資格を維持するために、その後2年以内にフォローアップ研修の受講が義務付けられています。費用は管理責任者講習会は10,000円。以後二年に一度のフォローアップ研修会は5,000円となります。
(2024年現在)。
-
入会に必要な書類の入手方法は? -

当会ホームページの入会ご案内にある「規定・申請書をダウンロードする」ボタン(もしくはページ最下段の「規定・申請書」)をクリックしていただき、「申請書類」のタグをクリックしてください。申請に必要なファイル(WORD文書)がございますので、ダウンロードしてお使いください。なおご不明な点は事務局までお問い合わせください。
-
「連絡窓口担当者」について教えてください。 -

●連絡窓口担当者 : SIAAからのご案内(会費請求書や講習会等のお知らせなど)は全て連絡窓口担当者の方にご連絡致します。
製品登録について
-
SIAAマークが取得できない製品の例とその理由を教えてください。 -

「登録加工製品の対象範囲に関する規定」(K30)では、以下のようなものを登録対象外の製品として規定しています。
[SIAA の安全性基準では安全性が考慮されていない製品]
・医薬品、医療機器、化粧品、医薬部外品(防護衣等、直接肌に触れる可能性が低い製品は除く)
・つけまつげ、まつげエクステンション、口腔材料等、眼や口等に触れる可能性のある製品
・24か月未満の乳幼児を対象とした製品
・一般消費者が使用するスプレー製品
・ペット用の食器 [評価試験ができない製品]
・耐久性試験や評価試験において、形状を保てない製品
[比較的長期間に渡っての効果発現が疑われる製品]
・バインダー等を配合していない後加工用製品(例:抗菌剤のみを分散させた業務用コーティング液)、
但し耐久性試験として耐水区分1で基準を満たしたものを除く。
-
あらたに製品を追加登録しようと思っております。登録までの日数はどのくらいでしょうか? -

申請書類が受理されれば、数日で手続きが完了します。
-
安全性試験データは、海外で取得したでもいいのでしょうか? -

SIAAの指定する安全性試験を行っている試験機関であれば国内でも海外の試験機関でも構いません。登録に必要な安全性データとは、論文や文献の値ではなく、具体的な試験報告書番号の記載をお願いしております。
-
プラスチック製品の原料となる「マスターバッチ」や「コンパウンド」を登録しようと思いますが、登録の分類は、<剤(加工剤)>でしょうか、<加工製品>でしょうか? -

<加工製品>としての扱いとなります。
-
テーブルクロスは布製品にも見えますが、登録できますか? -

後加工で機能を付与したテーブルクロスやバッグ等の日用品で撥水性がある製品(水が浸み込まないもの)は、繊維の評価方法※1よりも、SIAAの方法※2の方が適切なものは登録できます。「登録加工製品の対象範囲に関する規定」(K30)をご参照ください。
※1:JIS L 1902、JIS L 1922、JIS L 1921等
※2:JIS Z 2801、またはISO 21702
-
登録していた製品が製造中止となります。手続きについて教えてください。 -

「製品取下げ申請書」(FB6)をご提出ください。
書類には取下げ理由と、ホームページの登録加工製品検索ページの以降の扱いの希望についてご記入ください。SIAAマーク表示については製品在庫のある一定期間は継続してご利用いただけます。
-
登録したプラスチック加工製品で、原料の樹脂の購入先が変更になります。登録変更が必要でしょうか? -

樹脂の種類とグレードが変わらない場合は、変更登録の必要はありません。たとえば、A 社のPP(基材)をB 社のPP(基材)に変更、もしくはそれらを混合したPPに変更する場合は、PP には変更がないと解釈します。樹脂の種類が同じであっても成型グレード(ブロー成型用、押出成型、射出成型用など)が違う樹脂への変更の場合は、基本的にデータの取りなおし後に変更登録が必要となります。なお、登録製品の性能(抗菌活性、防カビ活性又は抗ウイルス活性)に影響を与えない、または与える影響が極めて小さいと判断される添加剤の変更などについては会員の自主判断に任せますが、念のため事務局にご相談ください。詳細は「製品登録マニュアル」(M25)で確認ください。
-
2つ以上の機能(例えば抗菌と抗ウイルス)を同時に登録し両マークを併記したいのですが、どのように登録するのでしょうか? -

それぞれ個別に登録申請してください。例えば抗菌+抗ウイルスであれば、抗菌加工品と抗ウイルス加工品として両方を登録し、抗菌活性と抗ウイルス活性の性能試験データがそれぞれ必要になります。なお抗菌剤と抗ウイルス加工剤とが同一でなく2剤併用使用の場合は、(混合の安全性を優先)別途薬剤混合に関する確認書類をご提出いただきますので事務局にお問い合わせください。
なお、入会と同時の申請の場合については、誓約書と入会申込書は1通で構いません。
-
登録した加工製品を部品として用いてあらたな加工製品を上市予定です。その場合、性能試験のやり直しや登録の変更は必要でしょうか? -

性能試験のやり直しは不要ですが、登録の変更は必要となります。副次的な要素のみを変更した製品は同等な加工製品として扱いますが、加工時に性能への何らかの影響が懸念される場合は、念のため性能活性を確認することを推奨しております。その場合、既に登録製品と加工部位や製品のジャンルが異なる場合は登録の変更が必要となります。
性能について
-
性能試験にはどのような試験法がありますか? -

試験方法については、各機能毎に、抗菌性能はJIS Z 2801法、抗ウイルス性能はISO21702法、防カビはJIS Z 2911 付属書Aに記載の方法B、抗バイオフィルムはISO 4768となります。
-
性能などの協議会自主基準はどのようにして決まったものですか -

旧通産省が主催した生活関連新機能加工製品懇談会作成の「抗菌加工製品ガイドライン」に準拠したかたちで、協議会「品質と安全性に関する自主基準」により自主基準が制定されました。これに伴い、SIAAマークの運用が開始されました。
-
自主登録データシートに記載する性能試験はどの試験機関で実施すればよいですか -

自主登録データシートに記載する性能データは、機能ごとに異なります。
指定試験機関の詳細は、規定K07「品質と安全性に関する自主規格」及びK07-2「登録製品別試験方法等一覧表」をご覧ください。
-
抗菌加工製品の性能基準が「抗菌活性値2.0以上」となっていますが、この値はどのような考え方で決められているのでしょうか -

抗菌性能評価は、微生物、すなわち生き物を使用した試験ですから、他の物性評価などに比べ、試験誤差が大きくなります。抗菌活性値が2.0以上であれば、誤差範囲ではなく、明らかに有意差があります。
-
耐久性試験とは何ですか -

「耐久性試験」とは、抗菌や抗ウイルス等の機能を付与した加工製品の機能試験を実施する前に、その製品が通常使用される環境を考慮して設定された条件で処理する試験をいい、実使用時の機能の耐久性や製品寿命を保証するものではありません。「耐久性試験」には耐水性試験と耐光性試験の2種類があります。詳細はK07-1「自主登録時の耐久性(耐水・耐光)試験区分(ガイドライン)」を参照ください。
安全性について
-
安全性試験について詳細を教えてください -

抗菌加工製品の場合、その安全性については使用する抗菌剤が協議会の定める安全基準を満たし、かつその使用濃度が安全性の確認された濃度以下であれば良いことになっております。(但し、抗菌剤を希釈して安全確認した場合は、安全性確認濃度の1/2以下)
抗菌剤の安全性の項目には次の4種類があり、全ての項目で協議会基準に適合しなければなりません。
<急性経口毒性試験>
ラットまたはマウスに薬剤を1回投与して、その死亡率からLD50値(50%の動物が死亡する薬量)を算出し、その値が2,000 mg/kg以上であることが必要です。LD50値が2,000 mg/kg以上であれば実際の取扱い上では無害と考えてよく、当然普通物に相当します(劇物はLD50値が300 mg/kg以下であり、毒物はもっと低い値になります)。また、動物愛護の観点からも投与量は最大2,000 mg/kgとなっています。
<皮膚一次刺激性試験>
ウサギの皮膚に薬剤 を塗布してその反応を調べた時に、刺激反応を認めないか、または弱い刺激性程度であることが必要です。皮膚一次刺激性指数で0~2が基準値となっています。
<変異原性試験>
微生物を用いたエイムス試験で突然変異性が無いこと(陰性)が必要です。この試験はアメリカの有名な遺伝学者であるAmes博士が開発した方法で、突然変異性を予測するのに適した方法として、広く認められているものです。この他必要に応じて染色体異常試験、小核試験を実施します。
<皮膚感作性試験>
皮膚感作性とは、ある薬剤に接触した後再度その薬剤に接触することによりアレルギー症状を引き起こす性質であり、多くの試験方法が知られています。その中でも厳しい方法とされているAdjuvant and Patch Test またはMaximization Testを採用し、その結果が陰性であることを必須としています。 ■ご注意 : 一部の医療機器の方法ではサンプルからの「抽出物」を試験に用いることとされておりますが、SIAAではあくまで「原体またはその希釈物」での試験を行うことになっております。「品質と安全性に関する自主規格」表9 安全性基準/注釈6)参照 )
-
安全性試験はどこに依頼すればよいか教えてください -

公的機関またはそれに準ずる機関において試験を実施してください。具体的な試験機関については以下が参考になりますが、必ずしもこれに限りません。 <安全性試験機関> 代表的な試験機関例として、以下の試験機関を列挙しました。安全性試験機関としてはこれ以外にも数多くあります。 協議会賛助会員 ① 一般財団法人 日本食品分析センター
住所 151-0062 東京都渋谷区元代々木町52-1
Tel 03-3469-7131 Fax 03-3469-1740② 株式会社 薬物安全性試験センター
住所 355-0166 埼玉県比企郡吉見町黒岩25-1
Tel 0493-54-3239
-
安全性の低い剤であって、そのままでは自主基準をクリアーできない場合、剤を水等の希釈剤で希釈して試験しても良いですか? -

安全性基準では抗菌剤としての安全性試験を原則としていますが、原体で基準を満たすことができない場合は、原体を希釈したもので安全性試験を実施し基準を満たすこととなっています。但しこの場合は、製品に使用する濃度は安全性が確認された濃度の1/2以下となります。
加えて、剤の成分として次の物質は意図的に使用することは出来ませんのでご留意ください。
・化審法施行令で第一種特定化学物質、第二種特定化学物質、監視化学物質に指定されている物質
・放射性物質、
・RoHS指令で規制されている物質
・毒物及び劇物取締法、又はその指定令で指定されている毒物又は劇物
・有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律および関連法規により規制されている物質
適正表示
-
SIAAマーク表示の原則、マークの大きさ、色について教えてください -

マークは、「基本図形」、「使用抗菌剤の種類、加工方法および加工部位を示す文字情報」、「登録番号」並びに「SIAAマークの主旨の説明文」から構成されます。
大きさは自由ですが、マークイメージが変わらないために縦横比の変更はできません。サイズ調整の際にはご注意ください。
マークには「標準色」を設定してありますが、マーク表示場所等の都合により単色であれば自由に変更可能です。ただし、グラデーションは認められていません。
-
SIAAマークを表示する場合、商品本体、販促物またはパッケージ等のどこに表示すれば良いですか。またそれらの全てに表示する必要はありますか。 -

SIAAマークは、会員が表示を希望する媒体(製品、カタログ、チラシ、取り扱い説明書、HP等)のどれかに表示する必要があります。
-
SIAAマーク表示が受理される前に、商品宣伝のため新聞等にマークを表示しても良いですか -

受理されるまでマーク表示はお待ちください。
-
製品中の一部に抗菌加工が施されている場合、SIAAマークはどのように表示すればよいのですか -

SIAAマーク管理運用規定に準拠します。基本的な考え方は抗菌性能を訴求している部分が分かるように表示することが重要です。消費者が誤認しないよう留意ください。
-
例えば「抗菌冷蔵庫」や「抗菌まな板」のような表示は可能ですか -

このような表示は”冠表示”と言われております。冷蔵庫の抗菌加工されている部位が一部のみなのにもかかわらず「抗菌冷蔵庫」と表示した場合、冷蔵庫全体が抗菌加工されているかのように誤まって認識されやすいので、この場合の冠表示は認めておりません。一方、明らかに製品全体が抗菌加工されている単一な樹脂製、例えば「まな板」については「抗菌まな板」と表示することは問題ありません。
-
SIAAマークのラベルはどこで入手できますか -

「SIAAマーク」基本図形のデザインデータをご案内しますので、これに従って会員各自で作製していただきます。協議会ではマークラベルは用意しておりません。
-
抗菌と抗ウイルス等、複数の効果があ場合、製品に複数のマークを表示出来ますか -

複数の表示は可能です。登録基準に適合し、それらを登録していただければ、1製品に複数のSIAAマークを表示できます。
-
当社のポリエチレンフィルムは、すでにSIAAマークを取得しています。客先がこのフィルムを加工した手袋を販売したいのですが、この加工メーカーが非会員の場合、SIAAマークを表示できるのでしょうか。 -

この顧客加工メーカーが貴社フィルムを使用した製品にSIAAマークを表示することはできません。マーク表示には、顧客が協議会に入会し、製品の登録をする必要があります。なおその登録の際、顧客は貴社フィルムの試験証明書を転用して登録することができます。
-
ひとつの製品に、部品として「無機抗菌剤を配合したプラスチック製部品」と「抗菌ステンレス製部品」とが組み込まれています。この場合の、ロゴマークの表示方法を教えてください。 -

登録は「部品」としてではなく、あくまで「製品」です。部品と部品の二箇所を抗菌加工した製品として登録していただくのでマークは一つになります。さらにSIAAマーク表示の文字情報には二つの加工部位についてそれぞれ記載されますので、二箇所に加工してあることがわかります。
-
薬機法および関連規制の禁止表示の例の中で、「菌やウィルスの名称を特定化して表示してはいけない」とあります。これは、一般ユーザーに渡る製品・カタログ・取扱説明書などには表示することはできないが、消費者に直接渡らない技術資料等であれば表示しても差し支えないことを意味しますか -

そのように理解しますが、技術資料であってもが、誤解を生じさせないよう表示の内容には十分ご留意ください。規定K32『加工製品の広告表記に関するガイドライン』もご参考ください。
-
スペースの都合で、協議会より指示された表示方法の全てを表示できません。そのような場合表示の一部を省略しても良いですか教えてください -

抗菌加工製品に表示のSIAAマークは、「基本図形」「使用剤の種類、加工方法および加工部位」「登録番号」そしてマーク説明文で構成されますが、文字情報、説明文がスペースの都合で記載できない場合は、別の箇所に記載していただいて結構です。記載箇所については事務局にご相談ください。
-
ISO 21702に基づきインフルエンザウイルスで試験をし、効果が認められています。試験ウイルスであっても記載不可ですか? -

試験ウイルスであっても、ウイルス名称の記載は不可です。インフルエンザウイルスや新型コロナウイルスの文言は、それらに関連する疾病を暗示させることから、薬機法に抵触する可能性が高いと判断されています。
-
SIAAに登録されている抗菌剤を用いて抗菌加工製品を製造しています。その製品にSIAAマークを表示できますか? -

SIAAマークを表示できるのは、SIAAに登録された製品のみです。登録するためには、必要な耐久性試験後、JIS Z 2801で抗菌試験をし、抗菌活性値2.0以上であることが必要です。SIAAに登録されている抗菌剤を使用しても、それだけではSIAAマークの表示は出来ません。
-
「SEKマーク」や「光触媒マーク」をSIAAマークと併せて表示してもいいですか? -

可能です。製品によっては複数の団体に登録(認証)されている製品もあります。消費者がそれらのマーク併記を見た際に、誤解を生じないようにすることが重要です。
運用について
-
品質管理や安全性の基準は決められていますか -

本会規定07「品質と安全性に関する自主規格」の中で、品質基準と安全性基準が規定されています。品質管理については「登録製品の品質管理に関するガイドライン」も併せてご参考ください。
-
当社では組織も場所も異なる事業所で複数の抗菌製品を製造しています。このような場合、複数の管理責任者が事業所毎か製品毎に選任する必要があるのでしょうか -

自主管理体制が確立されていることが会員の要件となります。管理体制が事業所毎であれば、事業所毎にその事業所で製造する製品について自主登録いただき、管理責任者についても事業所毎に選任することが望ましいと考えます。
その他
-
抗菌、防カビ、抗ウイルス、抗バイオフィルムは英語で何と言いますか? -

antimicrobial(抗菌)、antifungal(防カビ)、antiviral (抗ウイルス)、antibiofilm(抗バイオフィルム)といいます。
-
JIS やISOの試験方法 の資料はどうすれば入手できますか? -

「一般財団法人日本規格協会」にお問合せください。
